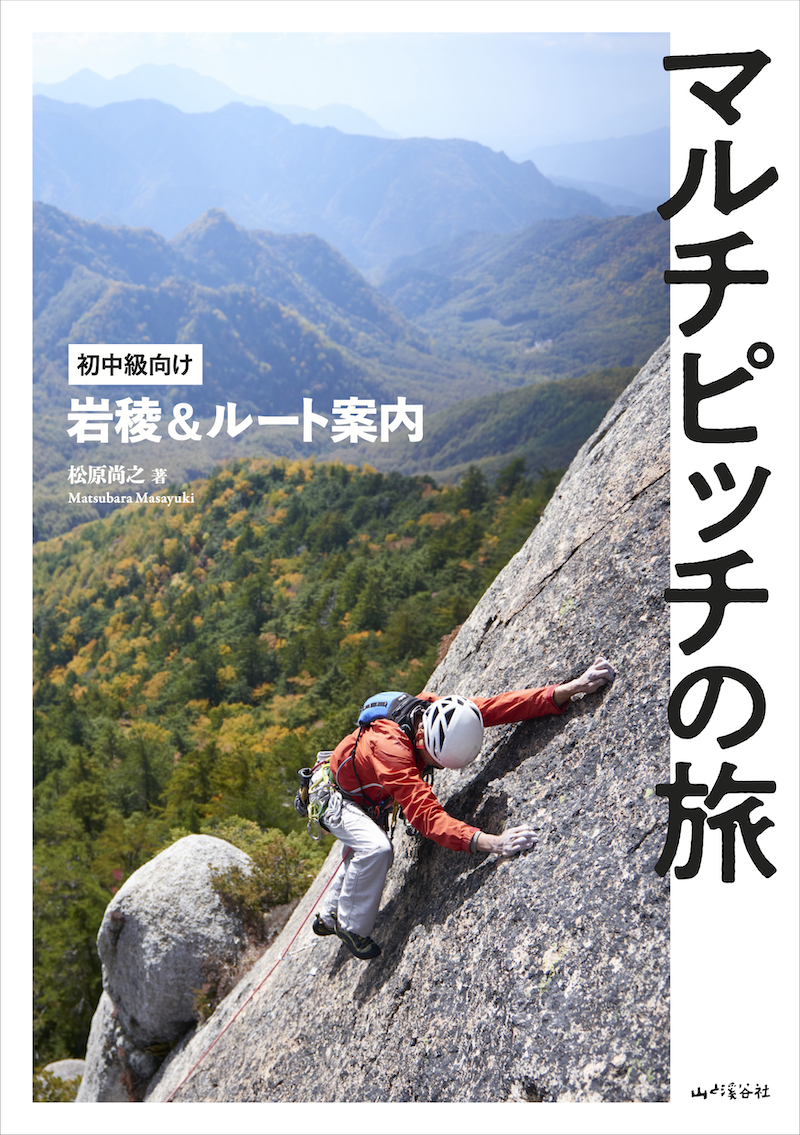- 基礎知識・ノウハウ
ボルダリング中にありがちな3つのケガの原因と対処法【インドア編】

高いところに登り落ちるという行為を繰り返すボルダリングにケガはつきもの。
分厚いマットが敷かれ、ほぼ平らな下地で登れるインドアのボルダリングジムはテクニックを向上させる上で欠かせない存在といえる。岩場でのボルダリングに比べれば、自分の限界に挑戦しやすいのは事実だ。
しかし、インドアでの事故や怪我の報告は後を絶たず、半分以上を占めるのが着地時のケガ。 それに次ぐのがムーブ中に体の関節や筋肉に負担がかかったことが原因によるものだという。 ケガは上達を妨げるもの。要注意だ。
今回はインドアのボルダリングでありがちな3つのケガの原因と対処法を探る。
1、着地
落ちる場所は意識しながら登ろう。

90年代は、着地時のケガといえば、マットの継ぎ目に足を挟んで捻挫したり骨折したり、というパターンが多かったが、現在はマットの質が向上し、継ぎ目はほとんどない。 にもかかわらず着地が原因となるケガが多い。
まず気をつけたいのはマットの端の段差を踏んだり、はみ出したりしてしまうこと。ボルダリングジムは落ちる範囲を想定してマットの面積を広くとってはいるが、これを超えてしまうことがあるようだ。
マットの位置を意識し、「ここで落ちたらあそこまで行ってしまうな」と下地を把握して登ろう。
無茶なムーブは控えよう

最近の傾向としてランジ(飛びつき)をすることが多いが、ホールドをキャッチして振り子のように体が振られたところで落ちると、とんでもないところまで飛んでいってしまうことがある。
マットからはみ出したり、片足で着地してしまったり、足から着地できずにケガをしたりする例が多数報告されているそうだ。 限界ムーブに挑戦できるインドアでもあまり無茶な課題をやらない方が身のためだろう。
高いところから飛び降りず、クライムダウンをしよう。

最後に、ゴールホールドを取ってからマットの上に飛び降りただけなのに、怪我をした例もある。
これを予防するには、できるだけ低い所までクライムダウンしてくるほかない。
たとえ、そのときは平気でも、長年ボルダリングを続けていると腰や首に故障が出てきた、という人を多く見かける。関節は消耗するもの。少しでも長く楽しむためにも、ゴールから飛び降りるのは避けるべきだ。
2、ムーブ中に・・・
疲れているときは登らない

ハイステップやキョン(ドロップニー)で膝を痛める。フットホールドが滑って、ぶら下がった瞬間に腕や指を負傷する。力を入れすぎて肩を脱臼するーーーなど着地時のケガに次いで多いのがムーブ中のケガである。
スポーツをするうえではある程度仕方ないケガだし、ボルダリングはどんどん難しい(ときには変態的な)ムーブを追求するものだから、これを予防するのは難しいが、体から発せられる痛みや疲労感に注意しよう。
例えば、普通は曲がらない方向に関節を曲げようとすれば痛みがあるだろうし、登りすぎで疲労がたまっていても体が痛かったり、だるかったりするだろう。
当然、疲労時はケガをしやすい。体は回復に48時間を要し、その前にトレーニングをしてもあまり効果がないというし、ケガは上達を妨げる最も大きな障壁だ。
3、人とぶつかる
登っている人の下にはいない

あまり多くはないが、インドアならではの事例として紹介しておきたいのは、フォールした人と下にいた人がぶつかってケガをするパターンだ。
どこのジムでも「マットの上では休まない」、「先に登っている人がいるときは近くの課題を登らない」などのルールを告知して注意を促しているが、混雑しているときやビギナーが多いときは混沌として危ないシーンはよくある。
これは相手がいることから責任の所在でもめることがあり、ケガをしたほうも、させたほうも嫌な思いをすることなので、絶対に避けるべき事故だ。特に小さな子供が大人の下敷きになるなどということはあってはならない。子供をボルダリングに連れて行くときは、片時も子供から目を離さないようにしたい。
捻挫をしたら
よく言われることだが捻挫などのケガを負ってしまったら「RICE」の応急処置をしよう。
R =安静、I =冷却、C =圧迫・固定、E =挙上の順に行ない、まずは安静にすること。
受傷直後だけでなく、しばらくは安静にしないと治るものも治らない。次に氷嚢など(冷湿布は不可)でアイシングして炎症や腫れを抑え、テーピングなどで圧迫・固定することで壊れた靭帯などが伸びたままになってしまうのを防ぐ。そして、なるべく心臓より高い位置に患部を上げておくことで炎症の治まりを早めるというのが鉄則だ。処置後は専門医の診断を受けること。
※本記事は2017.10.30に掲載したものです。