- 基礎知識・ノウハウ
キッズクライミング はじめの一歩

ボルダリングジムをオープンしてから約2年。クライミングが東京オリンピックの追加種目に決まって注目度が急上昇したせいか、キッズクライマーも増えているように感じます。
ひと昔前は「クライミング=危険」というイメージからか、子供を積極的に登らせようとする親は少なく、登らせている親というのはほとんどが自身もクライマーでした。しかし、現在は危険な印象が薄れたのか、子供をジムに連れてくるクライミング未経験の親も増えています。 もちろん、クライミングが安全になったわけではありません。
特にルートクライミングでは、ミスをすれば致命傷を負ってしまう可能性が高く、インドアのボルダリングでも捻挫や骨折のリスクはあります。正しい知識と技術を身に着け、常に慎重に登る必要があるので、お父さん、お母さんも一緒にインストラクションを受け、一度は自身で登ってみましょう。
今回は、多くの人にとってクライミングの入り口となるインドアを中心に、子供がボルダリングを始める際のノウハウを紹介します。

≪高さに慣れる≫
高さからくる怖ささえ克服すれば、だいたい子供は大人より上手に登れます。ただ、公園の遊具が危ないからという理由でなくなり、木登りをしたら怒られるといった風潮が原因でしょうか……、最近、高いところを怖がる子が増えたように感じます。以前はマットに飛び降りることを怖がる子供はそれほど多くなかったと思いますが、今は怖がって降りてこられなくなる子もたくさんいます。
ジムによってはキッズ用の低い壁があったり、子供用課題のゴールを特に低く設定したりしていますが、さらに安全に高さに慣れるために以下の3つをやってみましょう。
1 低い場所でクライムダウン(自分で壁を下りる)を練習させる。
2 低い場所で飛び降りる練習をさせる。
3 本人が怖いと言ったら無理をさせず、ゆっくりクライムダウンさせる。
スポット(下からのフォロー)をする人もいますが、私はあまり推奨していません。しっかりした技術がなければ落ちたときにぶつかってしまう可能性がありますし、子供であってもケガをしないように自分でコントロールできるようにならなければなりません。
無理さえさせなければ、ほとんどの場合、子供たちは自分で降りてこられるので、あまり手を出さないようにしましょう。

≪シューズを選ぶ≫
「フットホールドにつま先で乗る」というのは基本的なテクニックですが、まずは自由に登らせてあげましょう。つま先でホールドに乗らなければクライミングシューズを履く意味はあまりないとも言えます。初めてであれば、学校用の上履きで代用しても構いません。
また、レンタルシューズを履くときは、サイズは小さすぎないものを選びましょう。小さすぎるシューズを履いて痛くなっては楽しめません。
もしマイシューズを購入することになったら――
1 あまりタイトなサイズは履かせない。
2 ソールの柔らかいモデルを選ぶ。
3 ダウントウ、ターンインのきつい靴は選ばない。
足の発育を妨げず、フットホールドを掴む感覚を養い、自由でのびのびした登りをするために、子供用シューズを購入するときは以上の3点に注意してみてください。
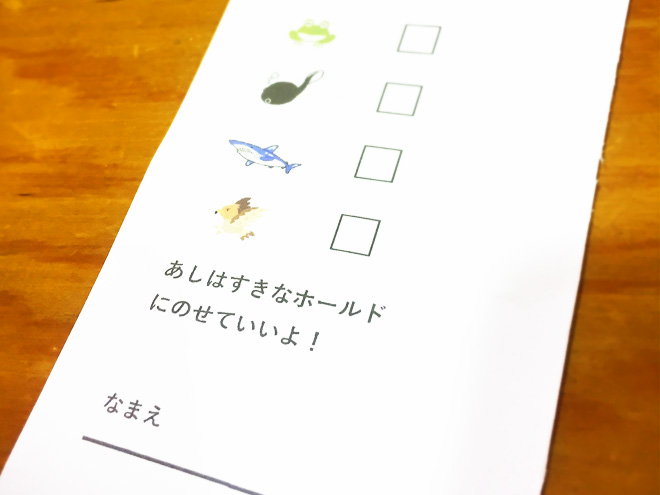
≪手指の皮の保護≫
皮膚が柔らかいせいか、たくさん登りすぎるせいか、登っているうちに手指の皮がベロッと剥けてしまう子をたくさん目にします。登り始める前にテーピングテープを巻いてあげるといいでしょう。あくまで皮膚の保護ですので、動きを妨げないように緩く巻きます。テープは12㎜のものを。もしそれで余ってしまうのであれば、19㎜を半分に裂いて使用しましょう。
また、トイレのとき以外にもやたらと手を洗う子を多く見ますが、濡れると皮が柔らかくなって剥けやすくなるので、必要以上に手洗いはしないように。
≪オブザベーション≫
ある程度登れるようになってきたら、オブザベーション(下見)をしましょう。小学生の低学年ではおとなしくイメージを膨らませるのは難しいかもしれないので、まずはじっと壁を見ることから。記憶できなくてもいいので考える癖をつけるのが重要です。
お父さん、お母さんが、ホールドひとつひとつを指しながら「このホールドはどっちの手で取る?」といった感じで一緒に考えてあげるのもいいでしょう。

≪まとめ≫
子供たちは目を輝かせて無邪気に壁に向かいます。初心者のうちは、多少、ムーブが間違っていても、あまり口を出さずに見守ってあげましょう。そして、ぜひお父さんお母さんもいっしょに登り、子供たちがどれほどがんばっていて、どれほど怖いかを知っておきましょう。
*ジムによって年齢制限があったり、利用できるエリアや時間に制限があったりと、それぞれルールが設定されています。事前に確認しましょう。
※本記事は2017.06.07に掲載されたものです。



